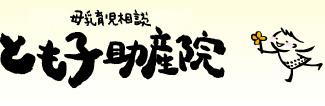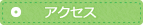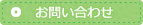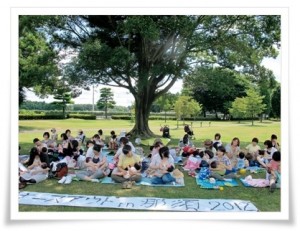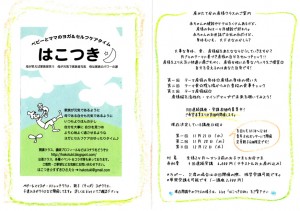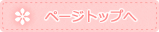毛糸のおっぱいプロジェクトで、オッピにタグ付けをしてくださっているおばあちゃまに、新生児用の帽子とおくるみを縫ってもらいました。
丁寧な仕事で、赤ちゃんもここちよさそうです。
とも子助産院で出産のお子さんへのプレゼントにしています。
バリエーションを増やして、近い将来、販売へつなげたいなあと思い、試作を重ねているところです。
うまれたての赤ちゃんは保温が大事。
早期接触(いわゆるカンガルーケア)のときに、赤ちゃんが冷えないように帽子をかぶせているのですが、3000g以上の成熟児には市販品はちいいさすぎて、すぐ脱げてしまいます。ちょうどよいサイズの帽子が欲しいなあとおもって開発しました。1枚500円。黄色・ピンク・ブルーがあります。
赤ちゃんのおくるみは、おっぱいやウンチで汚れることの多いものだから、肌触りが良くて、洗濯しても乾きがいいものが欲しくて、開発。赤ちゃんをよくバスタオルでくるんだりしているけど、洗濯しているうちにごわごわしてくるし、なかなか乾かないから、汚されると「あ~~」って気持ちになっちゃうでしょ。でも、これは、あっという間に乾くので、洗濯がおっくうじゃなくなります。
支援物資でいただいた、古ーいミシンをだましだまし使って、温かで軽いベロア生地と綿プリントをはぎあわせて制作しています。ちなみに布のチョイスは、山田助産師です。
ママ達には、なかなかの好評。興味のある方は、助産院にみに来てください。1枚1500円でおわけしています。
被災女性の手仕事が、少しでも現金収入につながるように、智恵を絞り中です。